銀行の中小企業向けファイナンス
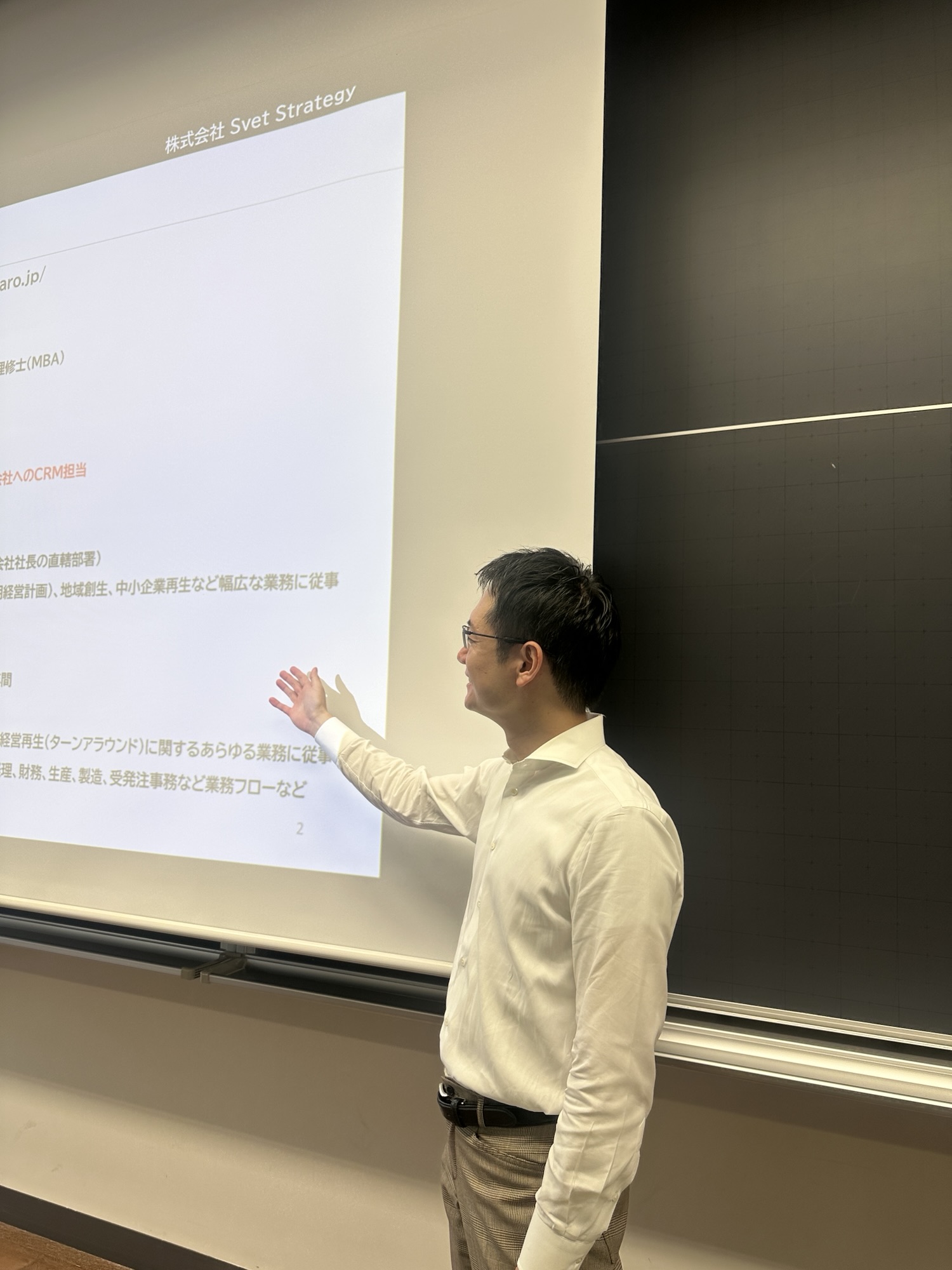
先週、母校青山学院大学で、大学2年~4年生向けに授業を行ってきた。
経済学部の授業で「銀行の中小企業向けファイナンス」という題目。
どのような講義をしようか初めに考えたのは、自分が大学生の時にいわゆる知識型の「お勉強授業」は…だったことを覚えている。
一方”考え方”を授けてくれた授業は今でも覚えているな、と。
金融実務が分からない20~22歳の大学生に、できるだけ専門用語を使わずに90分の時間を使って”考え方”を伝えるにはどうしたら良いか。1週間考えた。
今回の構成は、
1.事業をする際にお金を借りるとはどういうことか。仮に、今すぐ書店を始めたい。500万円必要。でも、お金がない。お金を貯めて数年待つ?借りることで今すぐ始める?
2.お金を借りる時と貸す時は考え方が違う。貸す時は相手のことをよく知る必要がある。方々にお金を借りてる友達に、自分のお金を貸せますか?
3.銀行も同じ。銀行のお金ではなく、自分のお金を貸せるかのように考えることが大切?あなたは年10万円の利息のために、1,000万円を貸すリスクを取れますか?
4.経営戦略、事業戦略はすごく大切。でも一番大切なのは、会社の社長。どんな魅力的な事業もやるのは人だから。そのために社長に何を聞く?
5.最後に”某スキマバイト社”を事例に、事業内容・経営戦略・経営者・財務内容・リスクを銀行員の目線で解説。
最後に「あなたがその某社から100億円貸して欲しいと言われたら、貸しますか?」を課題とし、稟議書を作成書いてみる。
学生の印象に残ったポイントは、
・お金を借りることと、貸すこと、時間を買うことの意味を知れた。
・金額が大きく、100億円ともなると感覚がなくなってくる。でも、どんな場合でも自分のお金でも貸せるかどうかは銀行員として持つべきことだと知った。
・銀行は数字で機械的に物事を判断してそうなイメージがあったが、事業は人であり社長をよく見ることの大切さを知った。
今回感じたことは、
「大学でもコンサルティング型ではなく、伴走型の教育が求められていそう」
どういうことか。大学生と社会人の間には相応のミスマッチがあり、新卒の会社を3年以内で辞める人は3人に1人も存在する。
銀行に就職したり、会社経営をはじめた時に、学問が役立つのは少し先。実務に根ざした「具体的な事例を元に自分のあたまで考えることを助けること」こそが、学生とのミスマッチだけでなく、の世界観を広げるのだろう。
つまり、大学教育と実践の場の違いで考えると、
ファイナンス理論でROEを学んだり、経営戦略をポジショニング(≒マーケット)やケイパビリティ(≒事業運営能力)学ぶことは大切。
でも”某スキマバイト社”を事例に、事業内容・経営戦略・経営者・財務内容・リスク ”を評価して、実際に100億円を貸せるかどうか自分のあたまで考えてみる。ことができないと、実学にはならないだろう。
前者がなくとも、後者があれば、生きていけるのだから。
最後に…
この授業日は、前日に4時間かけて福井市に行き、会食でしこたま飲み、5時半に起床。新幹線で10時半に渋谷に着き、11時から90分しゃべり続ける。家に戻って、夕方から娘の誕生日のためディズニーへ。翌日9時~21時までディズニー。
そう、経営者には常人じゃない体力を持ってる人が多いという話をし忘れた。
そんな話もセンセーショナルでありながら、経営者の現地現場だ。