マルクス「資本論」を読んで…
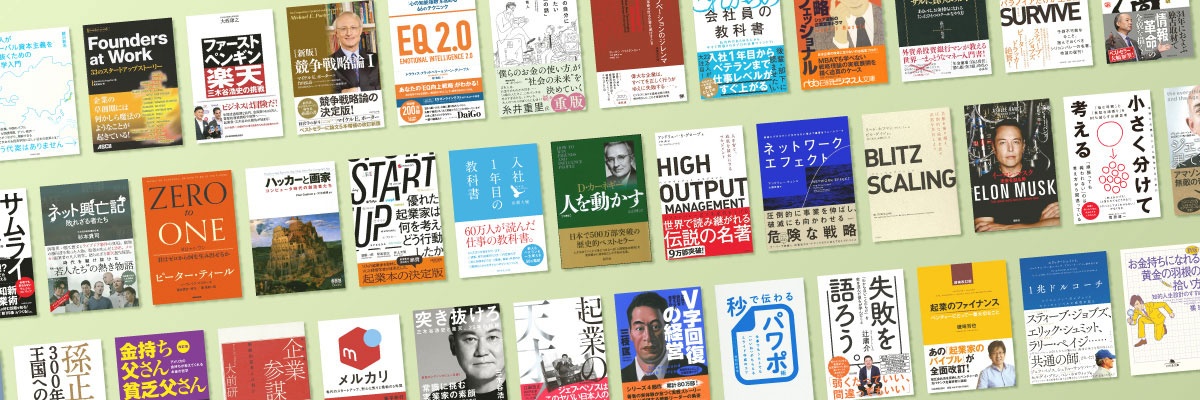
資本論の概要
ーーーーーー
猛威をふるい続ける新型コロナウィルス禍。それは人々の健康だけでなく、世界経済に大きな打撃を与え続けています。派遣労働などの非正規労働者の切り捨て、サラリーマンの給与カットやリストラ、相次ぐ中小企業の倒産等々…すでにその影響はじわじわと現れています。アフター・コロナの経済対策は、今、喫緊の課題として我々に迫ってきています。
そんな中、今、再び19世紀の思想家カール・マルクスの著作が多くの人たちに読まれ始めています。とりわけ私たちがその只中で生活している経済システムの矛盾を明らかにしてくれる『資本論』が大きな脚光を浴びているのです。
マルクスという名前を聞くと、ソ連や東欧諸国の崩壊以降はもはや時代遅れの思想と考える人も多いかもしれません。ところが、最近少し違った流れも出てきています。驚いたことに、アメリカでも、マルクスの名前が、若者たちのあいだで肯定的に使われるようになっています。アメリカの若者たちは、日本の若者たちと同様に、大学のローンを背負って社会にでても安定した仕事がなく、気候変動が深刻化する未来に不安を募らせています。そうした中で、資本主義では問題は解決しない、もっと抜本的改革が必要だとして、新たな社会像を考えるためのヒントをマルクスの思想に求め始めています。また、バルセロナ等の都市では、住宅や水、エネルギーといったコモン(共有財)を、利潤のみを追求し続ける大企業から市民の手に取り戻し、自分たちの力で水平的に共同管理していこうという試みも始まっています。それは、マルクスが「資本論」で「アソシエーション」と呼んだ仕組みに極めて近いあり方といえます。
経済思想研究者の斎藤幸平さんは、ソ連や中国といった既存の社会主義国家にはなかった全く新しい社会ヴィジョンが、マルクスがその生涯をかけ執筆した大著『資本論』のうちに眠っているといいます。マルクスによる「商品」、「貨幣」、「労働」、「資本」などについての鋭い分析は、執筆された150年前の当時と今では状況は異なっているにもかかわらず、全く古びていません。その可能性を読み解くとき、私たちが、今後どのような社会を構想すべきかという大きなヒントが得られるというのです。
世の中には『資本論』のたくさんの入門書はありますが、『資本論』に眠っている、将来社会という観点から読み直すものはあまりありません。そこで、番組では、グローバル資本主義社会が行き詰まり、その暴力性をむき出しにしつつある中で、もう一度、別の未来の可能性を、マルクスの代表作『資本論』を通して考えてみたいと思います
https://www.nhk.or.jp/meicho/famousbook/105_sihonron/
ーーーーーー
資本論は社会主義的思想の原点となったとされている。
実はそれだけでないことがよく分かる。
資本論は資本主義が発達してきた過程を色々なケースで分析し、その問題点を拾い上げている。
マルクスは、商品に使用価値と交換価値と定義して、それらを手に入れるための基礎にあるのが労働であると定義した。
商品の価値が労働に裏付けられているとすれば、商品価値に見合う分だけ働けば良いということである。
しかしここに資本家の概念が加わると話が変わってくる。
資本家は商品価値以上に労働者を働かせることにより、超過価値(余剰価値)を得ることになる。
まさに、資本家にとっての利潤になるということである。
だから、資本家は長時間で過酷な労働を強いるインセンティブが働く。
しかし様々な規制や労働市場圧迫(人手不足)により、働く時間に制限がかかったり、労働者の賃金が上がったりする。
そうすると超過価値を得るために、労働者に少ない時間で同じ超過価値を得られるように機械を導入することで対応しようとする。
機械により、少ない労働で超過価値を稼げるようになった資本家は労働者を解雇し、賃金を下げる。
その結果としてコストが下がるようになると、労働を強いた方が機械導入のコストを下回るようになり、資本家は労働者を雇うようになる。
このような景気循環をしていくということである。景気循環には恐慌という痛みを伴う。
痛みを伴う景気循環を繰り返すくらいなら、それを計画的に自らが作ってしまえば良い。問題は解決すると思ったのだろう。
様々な経済論者が論じているように、マルクスの主張にはいくつかの矛盾点が存在する。
労働を時間により定義して、その価値を均一とした点である。
確かに計画経済においては労働は時間で定義されると思う。
しかし現実において、人は様々な特性を持っており、その特性が万人にとっての価値
になるかどうかには差がある。
誰にでもできる仕事が得意な人と、人がやりたがらない仕事や人とは違う仕事をする人の間には、まさに時給の差があるように。
余談であるが、私はたまたま今の時代は経営者がお金を稼げる時代になっていると思うが、これが芸術によってしかお金を稼げない時代が来たのだとしたら、たちまち職を失うだろうと思っている。
たまたま、このパラダイムには対応ができそうというだけで、私も含めた経営者が人間として優れている訳ではない。考えている。
また資本論では、経済を物事を捉えようとすると、現実世界で行っている様々な思考を置き去りにしていまうことも問題だと思っている。
経済は所詮は一人一人の経済活動、選択ともいうべきことの連続性の先にあるものだ。それを踏まえなくては、描き出す全体が実態に即したものとなることはない。
理論と現実には大きな開きがある。
理論家は現実を知り現実の中から理論を導いていかなくてはならない(帰納法的)
現実家は目の前のことは得意かもしれないが長期的に見ると理論に収束することが多い。(演繹法的)だからこそ、理論を学び、活かさなくてはならない。
経営者はどちらの観点も持ちながら常に事に当たらなくてはならない。