【元メガバンク×経営・事業支援×ビジネスマッチング:鵜川太郎】経営を改善するために社内会議を変える~「現状の共有」で終わらせず「未来をつくる」場にしよう~
2025.06.16
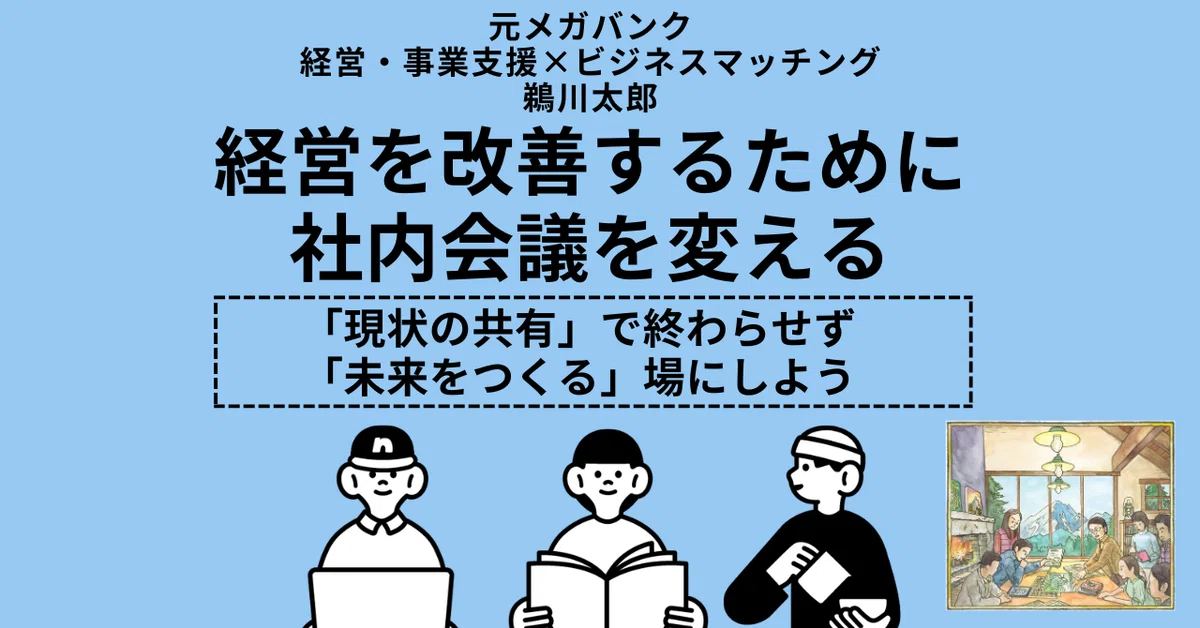
提供記事になります
https://note.com/arriba0519/n/n128de3a61122?magazine_key=me9023f2b43cc
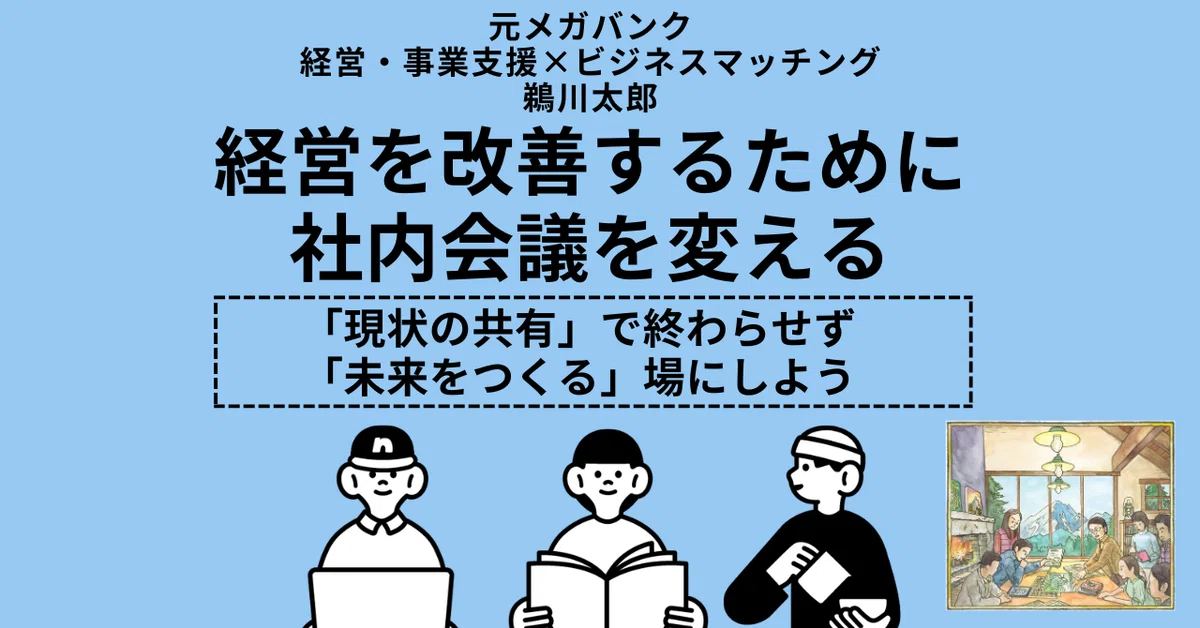
提供記事になります
https://note.com/arriba0519/n/n128de3a61122?magazine_key=me9023f2b43cc